
絡みあう鎖に、錆がこびりついていた。触れれば崩れてしまいそうな脆さを思わせたが、非常に堅牢だった。緑のネオンに包まれた室内には、仄かに煙が立ち込め、濡れた革靴が砂利の音を鈍く響かせて、液という液にまみれたタイルの床に、ねっとりとした泥を残していった。たわみ切った襞のうえでは、鉄製パイプが軋み、がなり声をあげ、剥き出しになった数多のそばかすが、陰に覆い隠された。眼窩の中に、遠い果ての場所が映る。かすめた風のにおいが髄液をゆすり、沈黙の響きに身がこわばる。
――朝焼けは、彩りを変えながら染みてゆく。鏡に映る君。澄ました微笑み。記憶が、爆ぜた。
絡みあう鎖に、錆がこびりついていた。触れれば崩れてしまいそうな脆さを思わせたが、非常に堅牢だった。
リンク
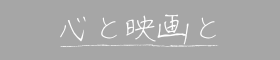
コメント