
東雲を見据える瞳。絡みのたうつ手。照らつく瑞々しい肢体。哀しみを知る唇。時として、人ひとりの重みは、世界のそれに匹敵する。雲霧を穿つ峰々より高く、人魚が眠る幾層もの闇より深い。日の光は、人を照らすから、美しい。
寂寥を纏う人がいる。雨は止まない。けれど、その人は、果てしなく、やさしい。独り佇む者の漂わせる気配に、散らばった孤独が引き戻される。懐かしい匂いに澱む部屋で、在りし日のか細い願いを思い出す。濡れた服を脱ぐ動作から、煙立つマグカップを胸元によせる手つきから、宛てなく彷徨う視線から、満ち満ちて塞きあえぬ静かな叫びがこぼれてくる。遺骨の残滓ほど儚い人の名残りを掬い取ろうとするやさしい姿勢で、霞む声に耳を澄ませ、瞬く表情に目を凝らし、頼りない温もりに肌を寄せれば、生の世界にも死の世界にも属さない、時間に取り残された人たちとの夢があらわれる。
青白い光が足元を照らす夜の端。蘇る感情に言葉で輪郭を与えるように、消えかかりそうな君の縁を指先でなぞる。この感触の名前は知っていた。愛だ。
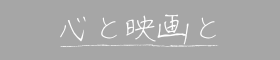
コメント