
「つまらない人」――。
時折、このフレーズが頭をよぎり、
心疚しい気持ちになるときがある。
原因は明々白々。私自身が、そういう人間だと自覚しているからだ。社会から要請される役割、組織のたてつけに沿った行動が求められる状態において、この憂いは生じない。しかし、ひとたびその枠組みの外に出てしまえば、時間が続く限り、私はつまらない人間となる。
「つまらない」とは、値打ちがない、張り合いがない、という意味だそうだ。ない、ない、ないとお尻につくが、では「つまらない人」というのは、この世に存在しない人のことを指すのではないだろうか。「あ、居たんだ」「あ、来てたんだ」と言われてしまう人のことを象る言葉なのではないだろうか。
あるのは常に、死の観念が染みついた崩壊寸前の肉塊と、その光景に愉悦を覚える者たちの好奇なまなざしだけだ。
…と、考えてしまう私を、そっと優しく包み込んでくれる、『時々、私は考える』は、そんな映画だった。

物語の主人公フランは、人付き合いが苦手で、職場の同僚との交流にも消極的。
たとえば、ある社員の送別会では、はじめの挨拶に参加するだけで、談笑が始まるやいなや、そそくさとその場を立ち去ってしまう。会話を持ち掛けられても、インフォメーションの羅列が続くのみで、血の通ったコミュニケーションが成立しない。
「つまらない人」と自称する彼女の日常、新しい同僚ロバートとのつながりを通じた彼女の感情の機微を追うのが、この物語の本筋だ。
なかでも素晴らしく美しいのは、ロバートと2人で、とあるパーティに参加した一夜である。そこで彼らは、サスペンス仕立ての物語になぞらえた遊びをする。(かくれんぼと演劇と人狼ゲームがセットになったもののようだ)指定されたプレイヤーは、死体役として、そのいきさつを説明するのだが、フランが独創的な死因を語り、場を盛り上げるというシーンがある。つまらない人と自称する彼女が、しっかりと人を笑わせる。人と人とが集まり、意味も目的もないままに、それでも子どものような面持ちで、その場で作用し合う光景は、その試みは、やはり尊いものだと確信するのに相応しい感動的なシーンだった。
「つまらない人」と自称する、「つまらない人」と自覚する…世界から自分を抹消するために用意したその言葉は、他者とのダイアローグが発生するたびに、いともたやすく打ち砕かれる。
職場のみんなのためにドーナツを買うと決めたフラン。彼女のことを知りたいと願うロバート。隙間なく抱擁をする2人の存在が、世界を象る。
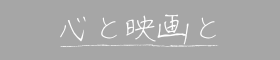

コメント