
エリック・ポッペ監督作品、映画『ウトヤ島、7月22日』の感想/紹介記事となります。
2011年7月22日、ノルウェー ウトヤ島で実際に起きた銃乱射事件に基づいた作品。この題材をもとにした他の映画も記事にしたためていますので、よかったら覗いてください。
(あわせて読みたい記事→【映画】『7月22日』思想を凌駕する”感情”【ポール・グリーングラス監督作品】)
凄惨なテロ事件を題材に、「死」をまえにした若者の恐怖を描いた本作。たいへん重い映画となっておりまして、観るのに体力を要する作品です。それだけに終盤、カヤが口ずさむシンディ・ローパーの楽曲「トゥルーカラーズ」がもたらす筆舌に尽くしがたい感動が印象に残ります。本作を観てからこの曲が好きになりました。
これは事実に基づいたフィクションであり、ドキュメンタリーではない。真実は一つにあらず。
引用:エリック・ポッペ監督からの言葉
こちらはエンドクレジットに表記される監督からのメッセージです。この言葉が意図することは、実際に起きた悲劇を「どう解釈し、また、どう語るかは観る者に任せましたよ」ということなのではないでしょうか。”フィクションにして伝える”という行為の意義を感じます。
本作をとおした私にとっての真実を以下に記していきます。
(※おおいに執筆者の主観がまじっていることをご留意ください)
(あわせて読みたい記事→【社会派ドラマ】特集「悲劇にみる人間の輝き」)
(音声はこちら→『ウトヤ島、7月22日』ただ、銃声と悲鳴だけが)
解説
2011年7月22日にノルウェーのウトヤ島で起こった無差別銃乱射事件を、生存者の証言に基づき映画化。97分間の本編のうち、事件の発生から収束までの72分間をワンカットで描いた。11年7月22日、ノルウェーの首都オスロの政府庁舎前で車に仕掛けられていた爆弾が爆発する。世間が混乱する中、オスロから40キロ離れたウトヤ島で今度は銃乱射事件が起こり、同地でノルウェー労働党青年部のサマーキャンプに参加してた10~20代の若者たちが犠牲になった。犯人は32歳のノルウェー人のアンネシュ・ベーリング・ブレイビクという男で、極右思想の持ち主であるブレイビグは、政府の移民政策に不満を抱きテロを計画。政府庁舎前の爆弾で8人、ウトヤ島の銃乱射で69人と、単独犯としては史上最多となる77人の命を奪った。映画は同テロ事件のうちウトヤ島での惨劇に焦点を当て、サマーキャンプに参加していた主人公の少女カヤの視点から、事件に巻き込まれた若者たちが恐怖や絶望の中で必死に生き抜こうとする姿をリアリズムたっぷりに描いた。監督は「ヒトラーに屈しなかった国王」「おやすみなさいを言いたくて」のエリック・ポッペ。18年・第68回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品。
映画.com
4つの「○○ない」
この映画では凄惨な銃乱射事件がリアルに描かれます。リアルを表現するために本作では、ほかの映画では「あるであろうものが、ない」ことに気がつきましたので記していきます。
①「カットがない」
まず特筆すべきは、ワンカットの映像表現です。72分間続いたウトヤ島での悲劇をワンカットで撮影し、表現することで観る者も実際にその島にいるかのような感覚に陥ります。くわえてクローズアップショットで人物たちの喜怒哀楽の表情を映すことで臨場感を演出したり、パンを繰り返すことで、さも自分が首を振り、辺りを見渡しているように思えてくるんですね。
カットをなくし、これらカメラワークを多用することにより、没入感がえぐいんです。
創られた映画を観ているのではなく、スリラー映画の登場人物の一人として映画制作に参加しているような感じです。まるで一人称視点のゲームをしているがごとくです。
②「音楽がない」
この映画では音楽が挿入されません。あるのは、ただ、銃声と悲鳴だけ。
あかるい映画ならなおのこと音楽とは、作品世界に彩を与えるための欠かせない要素です。本作ではそれがないんですね。でも現実はそういうものですよね。もし当時、現場に私がいたとしたならば、音楽なんて聴いている暇もありませんし、想いを馳せることもしないでしょう。
島を領するのは「死」を思わす銃声と、逃げ狂う若者の息遣いや悲鳴のみなのです。
実行犯は政治に関心のある思想をもった若者を標的としています。
思想 ⇒ 理性
恐怖 ⇒ 本能
とするならば…
銃声ひとつで思想が凌駕される瞬間が描かれているのです。
③「犯人が現れない」
「”死”を思わす銃声」と先述しましたが、本作では実際に引き金を引く人物をはっきりと描写していません。遠くにいる実行犯であろう人物をロングショットで納めてはいますが判然としないんですね。これもまたリアル。ただただ銃声から遠く離れるために逃げ回る人物に寄り添うのみで、対峙しようとする人物は向こう見ずな蛮勇でしょう。
そして、恐怖とは、「分からない」や「不明瞭」に対して抱く感情です。
当事者としては実行犯の正体も動機もわからぬままに、凄惨な事態に見舞われている状況です。あえて実行犯を映さないことで当事者と私たち鑑賞者に共通した恐怖心を抱かせる演出なのだと考えられます。
ただ、この恐怖を理解した気になってはいけない。映画冒頭にカヤが「分かりっこない」と第四の壁を越境して語りかけてきたのは、そのことだと思います。要は「これから起きるあらゆる悲劇を理解なんてできないよ」ということです。リード文で記しました監督からのメッセージもそのことの警告なのだと思います。自嘲しなさいねってことですね。
④「ヒーローがいない」
本作はキャンプに参加した若者がテロから逃げ狂う一幕を描きます。そこに”物語性”は感じられません。ハッピーエンドに終わる希望的観測もなく、アベンジャーズが助けてくれるような展開はまるで見込めない。
”いわゆる「映画」”的映画”で登場するようなヒーローを期待できないんですね。
あるのは恐怖というリアルのみです。
終始一貫して、犯行現場でジャーナリストがカメラを回し続けたような映像が続きます。カヤの視点に寄り添い、おなじく逃げ回る人物の様子を一緒になって覗く感じです。
映画をよく鑑賞する人なら展開をある程度予想することは可能だと思いますが、今作はそれが難しいんです。さきほど、恐怖の源泉を「分からない」や「不明瞭」と記しました。言い換えれば未来の予測不能性です。
物語の展開が見通すことのできない作品である、ということ自体が恐ろしいということ。実際の銃乱射事件の恐怖を、”物語性”の欠如で演出しているということです。
「死」がリアルなら、「生」もまたリアル
本作を観ての印象を1フレーズにすると…
恐怖の中においてさえ輝く人間の「生」
となります。
物語は恐怖の連続です。鳴りやまない銃声に、怯える若者の恐怖に満ちた表情と息遣い。たいへんリアルに描かれていて緊迫感が緩むことがありません。
なかでも一番に記憶しているものとしては、中盤で肩に銃痕ができた少女がカヤに介抱されるシーン。
例にもれずここでもワンカット撮影で映されていまして…
少女の「生」→「死」の過程をしっかりとリアルに描かれているんですね。
助けを請う少女のか細い声と痛みに耐える苦悶に満ちた表情。カヤの悲哀たっぷりに寄り添おうとする様子。そして、少女が声を発しなくなり、顔が青白くなっていく…というシークエンスです。どうやって撮ったんだ?と疑問になるくらいリアルに描かれていて、死にゆく瞬間ってこうなんだろうなというのが伝わってきます。
こうした恐怖を徹頭徹尾に描写し、ひたする逃げる若者たちをみます。
そして、「生」の実感というものは、「死」に対峙してこそ感じられるものだ、ということに気づかされます。
いずれ訪れる「死」という事実を前提にしているからこそ、「生」の価値を実感できるということ。この”生きていたい”という恐怖に対抗する「希望」が際立つんですね。
こんな状況でも、カヤが妹エミリエの安否を気にかけているということ。
こんな状況でも、マグヌスがカヤに冗談を発すること。
そして…
カヤが口ずさむシンディ・ローパーの楽曲「トゥルーカラーズ」。
銃声の鳴り響く島にて、それでも希望を語り、希望を唄う、ということ。
そこに人間の「生」の力強さを感じました。
まとめ
たいへん重い題材を扱った作品で、物語のトーンも終始暗いです。ですが全体に占めるそのリアルな暗さに滲む人間の明るさも確かに描いている作品であるとも思います。
またワンカットという映像表現のすごさを知るのにもよい作品ですね。
・緊迫感のある映画が好きな人
・生きがいを感じていない人
・ジャーナリスト志望の人
におすすめです。
ここまで読んでいただき、
ありがとうごじました。
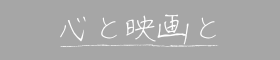
コメント