
影が、部屋の隅から、ゆっくりとあたりを包む。皮が剥がれ落ちた木製の椅子は、おもむろに色を閉ざしていく。鳴啼を吸いとる綿のカーテンは、窓の向こうで微風に揺らめく木々の葉と、静かに呼応する。埃が舞う。無為に、ちらちらと。絨毯の縺れ、積もり重なった塵、抜け落ちた体毛などが、頬をなでては、纏わりつく。しみが散らばる手は、物を探すことを諦め、むくんだ足の指先は、地面の踏みしめ方を忘れている。
無尽蔵かと思われた眠れぬ好奇心は、爬行する惰性の時間に呑まれ、かつてあれほどまでに滾っていた強い意志は、裏切りの記憶にひれ伏した。私を歓迎するのは、酒瓶の底にできた澱の王国だけだった。あまねいていた炎は消え失せた。
だが、いずれまた、立ち上がる。力が入らないのであれば、這ってでも、前に進んでいく。なるほどたしかに、多くの不信は世に憚る。次第に身体の節々も衰えていくだろう。しかし、それにより、どれだけ影に隠されようと、どんなに深く沈もうと、心という心は、燃える。火種そのものが消えることは決してない。生ある限り、走り、抱き、叫び、抗い、求め。人生に屈しはしないのだ。
黎明はひろがる――私だけの、美しい孤独。
リンク
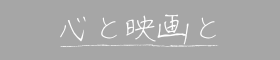
コメント