
一人の男が歩いている。歩みは軽やかではあるが、少し寂しい表情で、頼りない。妙に気になり、興味本位で尾行してみることにした。すると、同じ道をぐるぐるぐるぐると歩き続けていることに気が付いた。どうしてそんなことをするのだろうと疑問に思ったが、尋ねるのもおかしいので、その日は岐路につく。
翌日、また彼に出会った。昨日と同じように、所在なさげな表情で、ただただ歩き続けていた。想像もつかない何がしかの力が彼に作用しているのか。もしくは、彼自身の心が侵されており、同じ道を歩き続けること以外の選択肢を完全に取り払ってしまわれているのか。まるで、重力に逆らうようにと呪いをかけられた宿主なき傀儡のようだった。
10年後、私はとうの昔に離れていたその街を再び訪れた。理由は、次回作の物語の舞台を地元にしようと考えたためだ。小説家として暮らせるようになってからは初めての帰郷となる。駅の改札口を出る。建物も道路も様変わりしていた。学生の頃に何度も目にしていた風景は、もうその街にはなかった。だから、あの男とすれ違った時は、心底驚いた。だいぶ時間が経っていたからすぐに思い出せなかったけれど、確かにあの男だった。同じ道をひたすら歩き続ける不感症の男。私は立ち止まり、振り向いた。彼の背中が小さくなっていく。消えかかりそうになるほど、小さくなった時、声をかけてみようと思い至った。走りだした。彼との距離を詰めながら、次第に大きくなる背中を見つめ続けた。追いつき、声をかける。
「あの、すいません。お尋ねしたいことがあります」
男が足を止めた。徐にこちらへと向きを変えた。すると、その男の体が忽ちに空気と溶け合い、皓い空に果てていった。目の前に残されたのは、様変わりした街並みのみ。けれど、確かに私は見た。涙を浮かべて微笑む男の表情、心から祝福している人がみせるような嘘偽りのない優しさを。
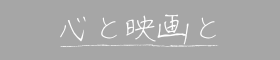
コメント