
白いフケが散った。服を剥ぎ、乾燥しきったざらざらの裸体があらわれる瞬間に、散った。それらがベットに舞降るまでの間、ミミズを目撃したときに見せる苦虫を嚙み潰したような面持ちを隠すことなく、その拘縮した四肢を眺めた。セミの抜け殻に似ていると思った。清拭をする。汗と糞尿に汚れた体を、可能な限り清潔にする作業。喧しい鳴き声に耐えながら、頑なな脚をこじ開け、生温かい鼠径部に湿ったタオルをあてていく。清拭を済ませ、新しい服に着替えさせている途中に、先輩の中谷さんがその体を指す名前を呼びながら、居室に入ってきた。
「お疲れ様です。変わるんで、佐良さんは休憩入っちゃってください」
僕は、頷きながら笑顔で返事をした。
帰りの電車のなか、最寄駅の二つ前の駅で下車しようと思い至った。歩くのが好きだった。踏み入ったことのない道、はじめてみる街並み、新しい世界との邂逅が、人生における数少ない喜びのひとつだった。下車し、雑踏を逃れ、帰途の方角に気を配りながら、進む道を直感的に選ぶ。五分ほど歩いたときには、人影がなくなっていた。こじんまりとした細い道に、白色に統一されたコンクリートの建物が所せましにそびえ建つ。夕日に染まる街路樹の葉が、風を受け入れながら優雅に踊っている。
いつも以上に長く歩いた。もう夜である。帰らなければと思いはじめた頃、暗い路地の先、交通機関へとつながる表通りに出たあたりのところに、やわらかく明かりの灯る建物を見つけた。ガラス張りのドアの向こうで、女性が独り黙々と作業に打ち込んでいた。その建物が、弦楽器を製作するための工房であると、彼女の姿と、工房名が記された立札を認めることですぐに気がついた。他者からの干渉がない自分だけの世界で、バイオリンを形作る器用な手さばきは、時間や仕事、人生をも手中におさめているかのように映った。単調なリズムで、さまざまな工程のあらゆる細かなカラクリを解きほぐしていく優美なひととき。海と大地がせめぎあう真夜中の渚ほど静かだが、弦楽器の創造以外の事柄を考える余地を与えない切実な情熱に満ちている感じがあった。ひび割れた木製の椅子に腰かけ、バイオリンのボディにあたるであろう木材にやさしく手をあて支えながら、片方の手で工具を操りアーチ状に削っていく。ただそれだけの光景だったのだが、工房までの細い通路の天井に垂れ下がる数多のバイオリンによる装飾もあってか、琥珀色に照らされた作業場が、日常から切り離された“異世界”を思わせた。どうせならこのまま、引き付け離さないでいてほしいと思えるほど、浮世離れした幸福が、心に染み入った。しかし、この世とも思えぬ素晴らしき光景は、面白みのない現実の磁場に、次第に収斂されていくものだ。異世界でのひとときは、そう長くは続かない。美しい心地が、容赦のない時間の濁流に押し流されてしまう。僕には、疲弊したこの体を木造アパートへと運ぶ作業が残されていた。
翌朝、セミの抜け殻がなくなっていた。異臭は微かに残るが、居室はもぬけの殻。これまでのこの場所における僕の営みが、過去の時間に呑み込まれたような感覚がした。……「近藤仁」。忽ち立ち昇った想念と、口をついて出てきた言葉は、その居室の主だった男の名前。思えば、僕がここで働きはじめた頃、彼はやさしかった。「ありがとう」が口癖で、入歯をはめ込むときも、他愛ない雑談のときも、車いすを押す最中にも、絶えず口にしていた。次第に、眼窩の裏に湛えた世界が侵されはじめると、無言の作業とではまるで調和しない、猛々しい喚き声しかがなり立てなくなっていったのだった。調和しないといえば、彼の体も同じようにミスマッチを起こしていたことを思いだす。手だ。手だけは、ひび割れ、いまにも裂けそうな薄い皮膚が大方を占める部位にくらべ、非常に頑丈だった。建設業、もしくは製造業だったか。ものづくりの仕事をしていたことによるものだと記憶している。手がけるのは、暮らしを守る家屋だったかもしれないし、産業を支える重要な機械設備だったかもしれない。もしくは、人のこころに触れる芸術作品の可能性も否定できない。インダストリアルな空間のなか、あのゴツゴツとした無骨な掌は、価値あるものを創造していたのだと思う。
創造に使われていた心と体が消失していくということ。かつて、あまねいていた創意は枯れ果て、磨き上げられた技巧も役に立たない。それ以前に、既にこの世から完全になくなってしまっている。不在を知らしめる仄かな臭いが、居室の空虚をより助長した。鼠色の厚い雲が引き伸ばされて、雨が降りだしていた。
彼女の手は、とてもしなやかだった。垂れ下がってきた前髪を、耳にかける仕草からは、甘い香りが見えた気がした。幻惑する僕のことを露知らず、透明ガラスの向こうで水滴に撫でられる彼女は、瞳を、指先に集中させていた。近藤さんも、あんなふうに特異な雰囲気を漂わせて、ものづくりに傾倒していたのだろうか。――「ありがとう」が口癖だった近藤さんのことに思いを馳せていたら、ドアが開け放たれる音が、耳をつんざいた。微笑む彼女が目の前に立っていた。びっくりして、死ぬかと思った。
「こんばんは」
と彼女。
「こんばんは」
と僕。
目のやり場に困る。異世界とは、こんなにも輝いているものなのか。
「興味あるんですか?バイオリン」
と言いながら、優美な指先で天井を指し示した。
「い、いやぁ~」
と言いながら、苦笑いしかできない。たぶん、すごく不細工だったと思う。
「そう」
束の間、残念そうに俯いたようだったが、すぐに気を取り直し、控えめで上品な笑顔を顕現してみせた。
「あの、淋しくはないんですか?」
と不躾な僕。
「淋しいって、仕事が?」
やや眉間に皺がよったが、怒っているわけではないと、彼女の目尻と口角を見て即座に判断できた。
「全然。だって、ほら」
と、片足を半歩引き、横向きになって、異世界への回廊の一部となった。
「綺麗でしょ?」
「はい、とても」
ようやく、彼女の瞳を見て、はっきりとそう答えた。
時刻通りに到着した電車に乗り込み、座席に腰を下ろした。ふと前に目をやると、バイオリンケースを抱える学生が、気持ちよさそうに眠りについていた。きっと、授業と部活で疲れているのだろう。電車で居眠りする人が、持ち物を落とすことはよくあるが、この学生にいたっては、その心配は無用のようだ。なぜなら、バイオリン専用のケースで守られているし、とても大事そうに抱えられているから。安心して、瞳を閉じた。そして、学生がバイオリンを演奏する姿を想像した。
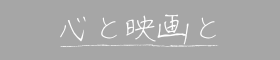
コメント